4月は新年度の始まりです。みなさんは疑問に思ったことはありませんか?外国では9月入学が多いのに、なぜ日本の入学式は4月なのでしょう。
江戸時代の寺子屋や藩校、私塾などは入学時期が決まっていませんでした。また、明治維新の頃、実は日本でも9月入学が主流だった時期がありました。
今回は、そんな歴史を経て、なぜ今日本の入学式は4月になったのか解説します。日本と同じく入学式が4月である国や入学式を4月にするメリットなどもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
日本の入学式はもともと何月なのか?
実のところ、日本の入学式はもともとは9月でした。明治維新で国が西洋の教育制度を導入した際、日本の高等教育学校や師範学校の先生の多くが欧米人だったため、欧米の制度にならって、日本も入学式を9月に行っていたのです。
そして、明治11年(1878年)に日本で最初の国立大学(現在の東京大学)ができると、9月に全員が一斉に入学、一斉に進級したほうが良いということになり、9月始まりで8月終わりの「学校年度」ができました。
では、なぜ欧米では9月に新学期が始まるのでしょうか?
一説には、18〜19世紀の農業事情が大きく関係しているといわれています。1年の中でも特に7~8月は収穫を迎える農作物が多く、その時期、農業を行っている家庭では子どもの手も借りたいほどの忙しさとなります。夏は家族総出で収穫を行わなければならず、子どもが学校に行く余裕がなかったのです。
こうした事情から、学校が始まるベストなタイミングは、農閑期に入って子どもたちの足並みがそろう9月とされたのです。
日本の入学式が4月になった理由
それでは、日本の入学式が4月になったのは、どうしてなのでしょうか?
これに関しては、大きく3つの説があります。
理由1 国の会計年度に合わせた
第1に、日本の入学式が4月になった理由として、「国の会計年度に合わせたから」というものがあります。会計年度とは、予算編成や決算などのスケジュールに合わせて1年の始まりと終わりを決めたものです。日本の会計年度は、主産業である稲作を基準として4月始まり、3月終わりになっています。
会計年度が導入された1886年当時、政府の税金の収入源はお米でした。秋にお米を収穫して、そのお米を現金に換えてから納税するには時間がかかり、1年の始まりを1月にすると納税が間に合いません。そのため、お米を現金化する期間を考慮すると、4月がちょうどタイミングが良かったのです。
理由2 イギリスの会計年度が4月だった
第2に、当時、世界1の経済力を誇り、日本にとって重要な国だったイギリスの会計年度が4月だったため、それに合わせて会計年度を4月にしたとも言われています。
いずれにせよ会計年度の開始が4月である以上、学校運営に必要なお金を政府から調達するため、学校も4月開始にした方が良いということで、日本の入学式が4月になったと言われています。
理由3 学校関係者が変更した
また、会計年度が4月始まりになったことで1886年(明治19年)に徴兵令が改正され、徴兵対象者の届け出期日がそれまでの9月1日から4月1日に変更されました。これに伴い、士官学校の新学期も4月となりました。
このことから「優秀な人材が徴兵されてしまう」と考えた学校関係者が、9月入学から4月入学へ早めたとも言われています。その後、全国の師範学校や小学校でも4月入学が広まり、大正時代に入ると高校や大学も4月入学に変わり、現在のスタイルになりました。
ちなみに、日本のインターナショナルスクールは、将来的に海外の大学を目指す人が多いこともあり、入学時期がずれないよう秋に始まる学校が多いそうです。
日本以外で4月入学の国一覧
日本以外で4月入学の国としては、インド、パキスタン、ネパールがあります。日本と同じ4月入学といっても、国によって入学後のスケジュールは異なります。この点も合わせて詳しくまとめると以下の通りです。
- インド:天候によって変わるが、夏休みは6月~7月末の中で 10日間と15日間の2回あります。冬休みは11月~2月末です。
- パキスタン:夏休みは約2カ月あり、宿題も多く出される。冬休みは1~2カ月間ある。寒い地域の冬休みは長いです。
- ネパール:夏休みは6月頃に15日間で、冬休みは12月に1ヶ月間、国民の祭りが10月末に15日間あります。
世界的に見ると、9月入学が主流です。4月入学の国は少なく、珍しいといえるでしょう。
このことから、4月入学だと欧米とスケジュールが合わないため、海外からの留学生や、日本から海外へ留学する人にとっては空白の期間(ギャップターム)が生じてしまうという問題が発生します。
4月入学のメリット
欧米にならい入学式を秋にしようとする動きがある中で、入学式は「やはり春」という人たちも多いのではないでしょうか。ここでは、そんな春入学のメリットについて詳しく解説いたします。
桜の咲く時期が入学式にあっている
4月はだんだんと暖かい気候になってきて、桜の花が咲いたり、木の芽が芽吹き始めたりと「始まり」を感じる季節です。こうした新たな門出としてふさわしい気候の中、入学式を執り行えるのは4月入学のメリットです。
学校の前で桜と一緒に記念撮影するのも入学式の定番といえますが、海外に合わせて日本でも9月入学になったら、まだ残暑の厳しい中で入学式をすることになります。
何となく新生活のスタートという感覚が薄れる、入学シーズンの風物詩となるものがなく物足りないと感じる人も多いのではないでしょうか。
国家資格や司法試験、就職試験などが春卒業を前提にしている
4月入学には、国家試験や司法試験、就職試験のあとにスムーズに仕事を始められるというメリットもあります。
日本の国家資格などは、基本的に春卒業を前提に試験日程が組まれており、就職試験も春卒業の学生を基準にしたスケジュールで行っています。
そのため、4月入学・3月卒業なら資格を取得したり、就職試験が終わったりした後、学校を卒業すればすぐに働き始めることが可能です。試験勉強で学んだことの記憶が新しい状態や、就職への熱意が高い状態で社会人になれるのです。
もしこうした各種試験のスケジュールが変わらないまま、入学月だけ9月になったら、学生は8月に卒業することになります。
就職まで半年ほど空白期間ができるため、社会人へのスムーズな移行がしにくくなる可能性があります。
また、この空白期間中、就職前の学生は無職となるため、各家庭で養ってもらう必要があり家計の負担も懸念されるでしょう。
現行の制度が4月入学に合ったものになっている
4月入学には、現行の各種制度にマッチしているというメリットもあります。2020年には新型コロナウイルスの流行を機に、9月入学への変更が議論されたことがありました。
しかし、1学年の人数がおよそ40万人増えること、教師・教室の確保や30以上の法律の改正が必要になるなど、多くの課題が生じることから懸念の声が上がり、最終的に見送りとなっています。
このことから、現行の制度や状況は4月入学に合ったものとなっており、日本においては現状、4月入学がフィットしていると言えるでしょう。
季節の始まりと合わせて生きている
本記事で解説した通り、日本の入学式はかつて9月だった時期もありますが、今は会計年度に合わせて4月となっています。
4月入学は世界的に見ると珍しく、グローバルな観点から見ると問題点も指摘されていますが、桜が咲く春に合わせて新生活をスタートさせることには、様々なメリットもあります。
現役の学生は春の暖かさや桜の開花で新しい生活へのワクワク感を膨らませ、大人たちは「自分たちも満開の桜の下で記念写真を撮った」と昔を懐かしむのではないでしょうか。
現在は9月入学導入に向けた動きもありますが、季節の始まりに合わせて生きるスケジュールは、日本人らしいとも言えます。
春になったら新しい生活に思いを馳せ、また1年頑張っていきましょう。

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-1.jpg)
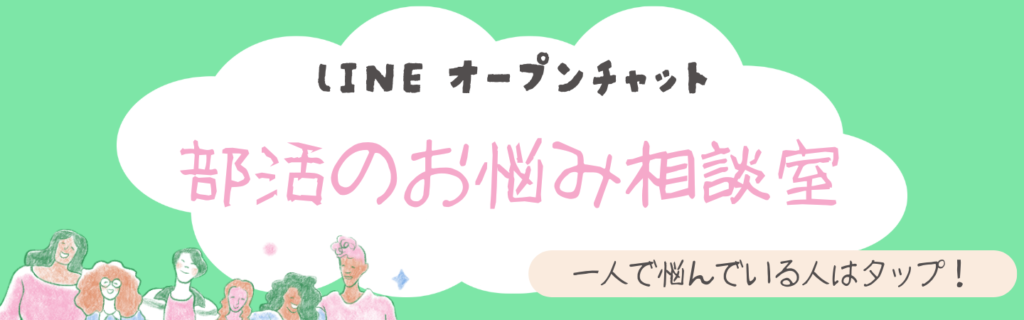

のコピーのコピーのコピー-18-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-19-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-4-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-21-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-23-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-18-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピー-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-2-1-300x173.jpg)
コメント