大学を卒業するにあたって、最後の難所が卒論提出だと言っても過言ではありません。とはいえ、「そろそろ卒論書かないと…」と思いつつ、1文字も書き始めることのないまま、気づけば提出期限の1週間前になっていた…。そのような状況に陥っている方もいるかもしれません。
卒論って万単位の文章量の論文を書くことになるので、億劫になってどうしても後回しになってしまいますよね。しかしそのまま放置していると、あなたは大学を卒業できなくなってしまいます。
大学を卒業できないと、これまで支払った学費が無駄になってしまいますし、企業から内定をもらっている場合は、内定先の企業にも迷惑をかけてしまうことになるでしょう。
そこで本記事では「1週間以内にゼロから卒論を仕上げる3つの秘策」を紹介します。卒論を書く際の注意点も3点紹介しているので、本記事を最後まで読めば、迷いなく卒論作成に取り掛かれますよ。
大学生生活の最後を、後悔なく締めくくるための最後のひと踏ん張りです。本記事の内容を参考に、提出期限までに卒論を完成させましょう。
卒論は出せばなんとかなる?
結論から言えば、卒論を出せばなんとかなるとは限りません。あくまでも、担当教員が卒論の品質を評価して、受理すると認めない限りは卒業を確定させることはできないと考えたほうがよいでしょう。
とはいえ、期限に間に合わないよりも、とりあえず出すことは重要です。1秒でも提出期限を過ぎると受理されなくなってしまうので、期限が1週間しかない人は、今すぐ卒論作成にとりかかりましょう。
論文としての体裁をしっかり整え、必要な文字数が満たされてさえいれば、内容がどれだけチープでも提出しないよりもはましです。再提出の時間を稼ぐことができるかもしれませんから、とにかく出すことを意識することをおすすめします。
1週間しか残されていないときにやるべき秘策3選
1週間という限られた時間で卒論を完成させるのは、大変高いハードルに思われるでしょう。以下で紹介する3つの秘策を実践すれば、作業効率が上がり卒論完成までの時間を大きく短縮できますよ。
その1 書きやすいテーマにする
本来長い時間をかけて作成する卒論ですが、期限まで1週間しかない場合は「自分がどれだけ書きやすいか」ということを重視してテーマを決めましょう。
「周りが感心するようなすごいテーマにしなきゃ」なんて考える必要はありません。
卒論は「提出期限内に完成させ提出すること」が最重要ですので「自分が書きやすいテーマ」をまず決めることが、1週間で卒論を完成させる第一歩です。
その2 問題を見つける
卒論は「学生が自ら出した問題定義に対して、考察や研究を行い、自分なりの結論を出す」ことが求められます。つまり「問題」が決まらないと、その先の考察や研究が行えないため、論文を書き進めることができなくなってしまいます。
最初に決めた「書きやすいテーマ」の問題定義をしてみましょう。問題が思いつかない時は、担当教授や他の学生に相談してみると良いですね。
その3 作業の順番を決める
1週間という限られた時間の中で卒論を完成させるには、とにかく無駄を省くことが大切です。作業の順番を決めておくことで「自分が今何をすべきか」が明確となり、雑念が消えて作業効率が上がります。
おすすめの作業順は「構成作成→データ収集→執筆(1章ごとに保存)→体裁整え→最終チェック」です。
「構成作成」では、大まかにどんな流れで論文を展開させていくかを決めます。各章でどんな内容を書くかを、1行程度で良いのでメモ書きを残すと執筆が進めやすくなります。卒論は明確な根拠を元に論理を展開させていく必要があるので、データ収集の時間も必要です。
文献を集めたり、自分でアンケートをとったりして、卒論の根幹を支えるための情報収集を行いましょう。「執筆」はスマホでもパソコンでも、使い慣れた方法であればどちらでも構いません。スキマ時間を有効活用するなら、移動中でも執筆できるスマホがおすすめです。
テーマや構成が決まり、論理を展開させる情報が揃えば、自分が思う以上にスラスラと執筆できるようになりますよ。卒論を執筆する際は「1章完成させるたびに保存すること」を意識しましょう。定期的に保存することで頭を切り替えられるので、集中力の低下を防ぐことができます。
また、卒論全体だと2万文字〜4万文字と膨大な量の文章を執筆することになるので、それだけで嫌になってしまいますが「まずは1章書く」ところまでハードルを下げれば、心理的にかなり書きやすくなるでしょう。
執筆が終わったら、提出するための体裁を整えます。作成した卒論を提出用ファイルにコピペし、段落を整えたり見出しのフォーマットを揃えたりしましょう。収集したデータの図解を挿入したり、参考文献の記載なども必要になります。
ここまでできたら卒論としては完成ですので、最後に細かいミスがないかチェックしましょう。誤字脱字や、参考文献の抜け漏れがないかなどを確認します。
ただ、提出期限1週間前で切羽詰まっている状況であれば「提出すること」が最優先ですので、最終チェックは「余裕があれば行う」程度で考えれば大丈夫です。
卒論を書くときの注意点
ここまでは「1週間で卒論を仕上げるための秘策」を紹介しました。本章では「卒論を書くときの注意点」を3つ紹介するので、作成に取り掛かる前に必ず目を通しておきましょう。
注意1 コピペしない
情報元として参考にした文献やWeb記事の文章を丸写しするのはNGです。「剽窃」と呼ばれるコピペ行為は、他者の創意工夫を盗用して自分の成果とするので、非常に悪質です。
どれだけ文章力に自信がなくても、参考にした情報を元に、自分なりの表現を使って執筆してください。情報元の文章をそのまま記載すべき必然性がある場合は、「引用」として記載しましょう。
注意2 書けるところから書く
卒論に限らず、長文を執筆する時は「書けるところから書き進めること」が、効率よく執筆を進めるコツです。
ある程度の長さの文章がまとまり「ひとつの章」として成り立ったものが、複数集まることで完成するのが卒論です。
心理的には頭から書き始めたくなってしまいますが、無理して順番に書こうとすると文章が思いつかず、手が止まってしまう可能性があります。
手が止まった分だけ時間の無駄ができてしまうので、順番は気にせず取り掛かりやすいところから、優先的に執筆していきましょう。
注意3 目次を先に決める
卒論の本文を書く前から、目次を決めておくことはおすすめしません。なぜなら目次を先に決めてしまうと、目次ありきで本文を展開させることになるので、書きにくくなるからです。
また目次を先に決めてしまうと、執筆中に内容の変更や追加があったときに目次も変更する必要があるため、二度手間になります。
卒論の構成は先に決めるのですが、あくまでも「どんな流れで論理を展開させていくのか」を決めるだけですので、目次を決めることとは少し違います。
構成がしっかりしていて、構成に合わせた本文がしっかり書けていれば、後からでも目次は作ることができますよ。
まずは提出して誠意をみせよう
卒論はとにかく「期限以内に提出すること」が最大の誠意です。1秒でも遅れたら、受理されなくなってしまいます。あまりにも提出期限ギリギリだと、担当教授に会うタイミングがなかったりインターネットの回線が混雑したりして、間に合わなくなってしまう可能性があります。
そのため、遅くとも提出期限の1日前には提出できるくらいの余裕を持って、卒論を書き進めると良いですね。記事で紹介した「1週間で卒論を書く秘策」を実行して、あなたの卒論が提出期限に間に合えば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-5.jpg)
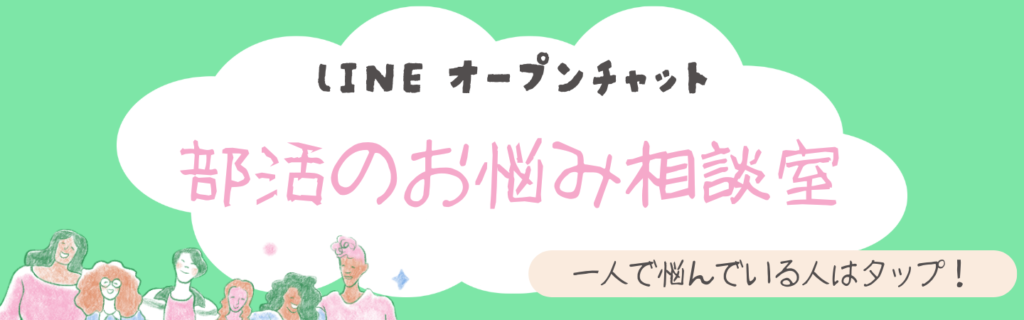

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-13-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-300x173.png)
のコピーのコピーのコピー-2-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-12-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-18-300x173.jpg)
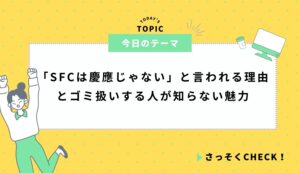
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-11-300x173.jpg)
コメント