みなさんのなかには、クラスの中で掲げる学級目標について悩んでいる人たちもいるはずです。なかには、具体的なアイデアとして四字熟語を取り入れようと考えている人もいるかもしれません。
とはいえ、具体的に、どのような言葉にすればよいのでしょうか?
この記事では、学級目標にぴったりな四字熟語を紹介しています。また、学級目標を考えるポイントも紹介しているので、参考にしてみてください。
学級目標とは?
学級目標とは、クラスで掲げる精神的なスローガンです。個性の異なる生徒たちが共通で意識することで、団結力を向上させたり、組織として動くときの指標になったりすることが期待されます。仲の良いクラスならば、振り返ったときの良い思い出になるでしょう。
日本の小学校、中学校、高校はクラスというコミュニティに所属して生活しますから、共同体という意識が重視される傾向にあります。学級目標がよりよいクラス運営を行うための精神的な支柱になることで、クラス替えや卒業のタイミングで「このメンバーでよかったな」という満足感に貢献するでしょう。
学級目標にぴったりの四字熟語まとめ
学級目標を決める際には、以下のようなタイプがあります。話し合いがまとまらない場合は、ある程度型を決めてしまい、それにみんなの意見や雰囲気にふさわしい言葉を当てはめていく方法もおすすめです。
- スローガン・テーマ型
- イメージ・比喩型
- 語呂合わせ型
- 熟語型
学級目標はシンプルな言葉の方が、記憶に残りやすいとされています。特に熟語型の一種である四字熟語はフレーズが短く、使われている漢字から目標をイメージしやすいので、おすすめです。
今回は、5つのテーマにふさわしい四字熟語とその意味を取り上げました。春の新しい学級目標を決める際に、参考にしてみてはいかがでしょうか。
その1 思いやりのあるテーマ
- 一視同仁(いっしどうじん):差別することなく全ての人に等しく接するという意味です。いじめのない仲の良いクラスなどのイメージにぴったりです。
- 仁者不憂(じんしゃふゆう):思いやりが備わっている人は、常に道理に従い自分にやましいことがないので、憂いを抱えることがないという意味です。
- 誠心誠意(せいしんせいい):純粋なまごころのことで。自分の欲や利益を交えずに、正直な態度で相手に接することを指します。
- 知者不惑(ちしゃふわく):本当に賢い人は物事の道理をわきまえているので、判断を誤ったり迷うことがないという意味です。勉強だけでなく、生きていく上での賢さを身に着けることを目標とする場面などにふさわしい言葉です。
その2 明るいテーマ
- 雲外蒼天(うんがいそうてん):困難の先には明るい未来があるという意味で、分厚い雲を困難、青空を未来に見立てた比喩の四字熟語です。
- 桜梅桃李(おうばいとうり):桜・梅・桃・李(すもも)のそれぞれが美しい花を咲かせるように、他人と自分を比較するのではなく、一人ひとりの個性を大切にしようという教訓です。
- 四海兄弟(しかいけいてい):世界中の人々は皆兄弟のように仲良くするべきだという意味です。転じて、礼儀と真心をもって人に接すれば、兄弟のように親しくなれるという意味もあります。
- 海闊天空(かいかつてんくう):心が広くさっぱりしていることのたとえです。そこから、無限の可能性や自由な発想を表す言葉として使われることもあります。
その3 メリハリのあるテーマ
- 慎始敬終(しんしけいしゅう):物事を始めから終わりまで気を引き締めて、やり抜くことです。始めと終わりが肝心だという意味でも用いられます。
- 万里一空(ばんりいっくう):広い視野で概況を見極め、落ち着いた態度で目標達成に向かうことです。目標を達成するためには、多少の出来事に動じない精神力が求められますね。
- 精神一到(せいしんいっとう)全精神を一つに集中すれば、どのようなことでも成し遂げられるという意味です。最善の結果を出すために全力を傾けて努力する姿勢は、学校生活のさまざまな勝負場面で欠かせないものだと言えるでしょう。
- 万能一心(ばんのういっしん):何事も心を集中させて学ばなければ身につかないということです。転じて、どれほど技芸をこなせても、真心が欠けていれば無意味だという意味も持ちます。
その4 かっこいいテーマ
- 有言実行(ゆうげんじっこう):言ったことは必ず実行するという意味です。他の人から信用されるためには、小さな約束などでも守りたいものです。
- 点滴穿石(てんてきせんてき):わずかな力でも積み重なると大きな成果をもたらすという意味です。こつこつと努力を積み重ねる人にふさわしい言葉ではないでしょうか。
- 百折不撓(ひゃくせつふとう):何度失敗しても志を曲げず信念を貫くことです。失敗しても諦めずに、夢や目標を達成しようとする受験生などにぴったりですね。
- 率先垂範(そっせんすいはん):人の先頭に立って模範を示すという意味です。学校生活であれば、人が嫌がる役目や仕事を積極的に引き受ける人や、リーダーなどにふさわしい言葉ではないでしょうか。
その5 協力を意識するテーマ
- 一致団結(いっちだんけつ):共通の目的に向かって、集団が一つにまとまることです。
- 切磋琢磨(せっさたくま):学問や修養によって自分を磨き上げ、仲間同士が競争・激励し合って向上を目指すという意味です。
- 和衷協同(わちゅうきょうどう):心を同じくして共に力を合わせることです。クラスの団結を深めることを目標とする場合などに。
- 一蓮托生(いちれんたくしょう):事の良し悪しに関わらず行動や運命を共にするという意味です。仏教用語に由来するもので、極楽浄土の同じ蓮(はす)の上に生まれ変わり身を托すということから、運命共同体の意味に転じました。
学級目標を考えるときの注意点
学級目標を考える際には、いくつか注意したいポイントがあります。
注意1 みんなが共感するものを選ぶ
学級目標は、先生から言われたままに受け入れるのではあまり意味がありません。クラス全体で目標を達成するためには、各自が自分の問題として捉え、実行していく必要があります。
そのためには、ホームルームの時間などを利用して、クラス全体で話し合いの場を設け、協力して決めましょう。皆で考えることで、自己実現や成長につながるだけでなく、一人ひとりの意見が反映されて統一感が生まれやすくなります。
もしどうしても決められた時間で決まらない場合には、先生にアドバイスを仰いでも良いでしょう。ですが、あくまでも自分たちの意志でクラス全体の合意形成にするように、心がけてください。
注意2 具体的な行動を伴うものにする
学級目標が決まったら、それを実現するための具体的な行動目標も併せて決めていきましょう。学級目標が抽象的な言葉のみでは、何となくイメージを思い浮かべるだけで満足してしまい、実際の行動につながりにくくなるからです。
たとえば、学級目標が高校受験に向けて毎日努力するという意味の学級目標が、「全員合格」だったとします。この場合、「1日4ページ分の家庭学習ノートを提出する」というように、具体的な行動目標も設定しましょう。
さらに、目標設定は高すぎても低すぎても達成感を得にくくなります。あくまでも目的は自分たちの成長ですから、今の自分よりも成長できるような目標を設定しましょう。
注意3 形だけにならないような工夫をする
中学生が学級目標を立てる時期は、多くが新学期の始めです。ですが、時間が経つにつれて目標が何だったか忘れてしまうことも、珍しくありません。
その原因の一つとして考えられるのは、目標の文章が長すぎるケースです。 たとえば語呂合わせの場合、頭文字に続いて一つ一つテーマが設定されます。それらを全て覚えるのは大変ですね。また、行動目標が実現できているかどうかを振り返るのも、当初の目標を見失わないための有効な手段です。
一例として、各月の最初のホームルームで、それぞれの目標に対する振り返りの時間を設けるなどの工夫をしてみましょう。各自がどのような行動を取れたか、翌月に向けて具体的な改善点はないかなどを振り返り、春に決めた学級目標を思い出すきっかけとするのも有効です。
みんなでゴールを達成した充実感は消えない
学級目標を決めるには、クラス全体の意識が共通の目標に向かってそろっていなければなりません。生徒が主体となり自分たちで運営方針を決めることで、学校生活のモチベーションアップや責任感にもつながるのです。
学級目標を決めるまでには、意見の違いや対立することもあるでしょう。ですがそれらを乗り越えて決めた目標は、皆の学校生活をより豊かにしてくれるはずです。自分たちにふさわしい目標を決めて、充実した学校生活を送ってください。

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-15.jpg)
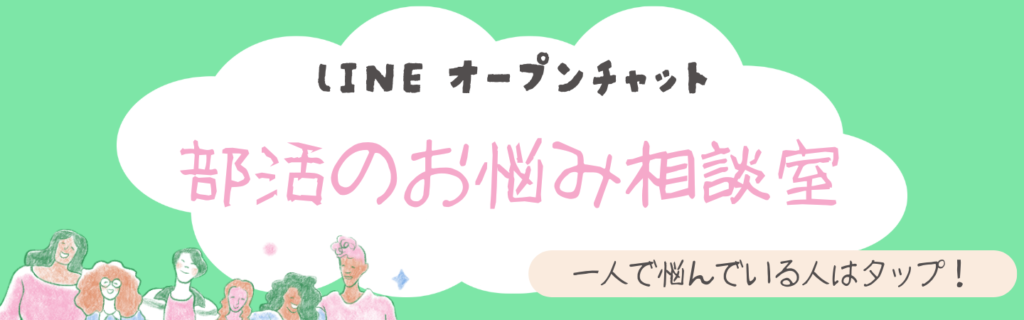

のコピーのコピーのコピー-26-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-27-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-4-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-3-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-4-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-300x173.png)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-6-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-300x173.png)
コメント