生徒会は、学校生活をよりよくするために生徒自身が運営する組織です。生徒全員の意見や要望を学校に伝える役割があり、学校生活におけるルールや行事の運営方法など、改善提案ができます。
本記事では、生徒会の組織構成や役職について解説します。適切な人数や役職の決め方についても紹介するので、生徒会について知りたい人はぜひ最後まで読んでください。
生徒会の組織一覧
生徒会の組織図は学校によって異なりますが、一般的には上記のような構造になっています。
組織の最高部となる生徒総会は全校生徒が参加する最高議決機関です。生徒総会では予算・決算の決議や、生徒会規約の改正について審議をします。
生徒総会の直下に位置する評議会は、各クラスの代表者や委員会の委員長が参加します。生徒総会で決まったことを具体的に実行するための計画を立てる会です。日常の問題を解決する活動もしています。
評議会の次の生徒会執行部は、日常の学校生活内の運営を担当します。会長、副会長、書記、会計、広報などの役職で構成される組織です。地域のボランティア活動に参加したり、学校行事の企画運営を行ったり、生徒総会や評議会への議案を検討したりと、仕事は多岐にわたります。
同じく評議会の下の監査委員会は、委員会や生徒会の会計に不適切な支出や計算間違いなどがないかを確認し、評定をつける役割です。
生徒会の役職一覧
生徒会執行部には、次の役職があります。
- 会長
- 副会長
- 会計
- 書記
それぞれが重要な役割を果たしています。ここからは、それぞれの役割について詳しく解説していきます。
役割1:会長
会長は、生徒会のリーダーであり、執行部全体の指揮を執ります。
生徒会長というと、卒業式や入学式で挨拶をする人を思い浮かべるのではないでしょうか。度々人前に出る生徒会長は、生徒総会や評議会での司会進行も任されます。
また、選挙期間中に自分に公約を掲げ、その公約を達成させるための活動も行います。時には生徒に、組織に、先生に働きかけを行い、自分で立てた公約を果たすことも大事な仕事です。
人前での挨拶を抵抗なくできる度胸があり、執行部だけでなく学校全体を引っ張っていく強いリーダーシップを持っている人が向いていると言えます。
役職2:副会長
副会長は、会長をサポートするのが主な仕事です。
日常の執行部業務の中で、会長が多忙なときに支援をします。会長の公約を果たすために裏方として動くことも重要です。
また、会長が不在の時には、会長の代わりに役割を代行することも重要な仕事の一つです。会長が万が一卒業式に体調不良で出られなくなってしまった場合には、突然登壇せざるを得ないわけです。
よほどのことがなければ表に立つことはありませんが、会長のサポートと同時に執行部全体を俯瞰して見渡す力が求められます。
役職3:会計
会計は生徒会のお財布を管理する役割です。
生徒会の収支を管理し、予算案や決算報告の作成も行います。各部活、各委員会への予算配分を行い、割り振ったお金が適切に使われているかを確認します。
収支を正確に記録することで、透明性を担保することも会計の仕事です。
会計は、細かい計算やコツコツとした作業を苦なくできる人が向いています。収支の計算が合わないときでも、あきらめずに原因を追及していく粘り強さも求められます。
役職4:書記
書記の主な仕事は議事録作成です。
生徒会の会議や、評議会、生徒総会などありとあらゆる会議で議事録を取ります。決まったことやそこに至るまでの議論のプロセスを記録していくことで、トラブルを事前に予防することができます。
広報という役割を生徒会執行部の中に置いていない学校では、書記が生徒会が発行する生徒会誌や生徒会新聞の記事を書くこともあります。生徒会の広報活動をサポートしていく役割も担っています。
大小かかわらず常に仕事があるのが書記です。速記ができれば難なく務められるでしょう。書記の仕事を通して、長い文章を要約できる能力が身につくかもしれません。
また、ニュースレターなどの作成も担う場合は、文章を作り出すスキルも求められます。
3.生徒会に必要な人数
生徒会執行部の適切な人数は、学校の規模や活動内容によって異なりますが、以下のような構成が一般的です。
| 役職 | 人数 |
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 2名 |
| 会計 | 2~3名 |
| 書記 | 3名 |
会長は全体の指揮を行うリーダーなので、1名の選出となります。
副会長は、全体を冷静に観察をしないとならない立場のため、実は業務が多く、2名選出されることが多いです。また、副会長を2名置くことで、意見の偏りをなくし、バランスの良い運営をしていくことができます。
会計は2名もしくは3名がよいでしょう。年度末には学校中の収支を確認しなければなりません。ダブルチェックをすることでミスを防ぐことができます。
書記も2名から3名いた方がよいとされています。議事を取らなくてはいけない会議が多いため、書記は常に業務があふれている状態です。複数名配置することで、効率的に仕事を進めることができます。
生徒会における役職の決め方
生徒会は、学校の運営において重要な役割を果たすことは触れてきました。そのため、生徒会の役職を決めるのも、慎重に行わなければなりません。学校の方針や生徒の意向によって決め方は異なりますが、一般的には、選挙、推薦の2つの決め方があります。
選挙は一般的な決め方です。全校生徒の投票によって役職を決定します。立候補者が自分の公約を発表し、生徒たちがそれをもとに投票します。選挙のやり方は市長選挙のようで、投票する側の意識も千差万別です。
生徒全員が投票者として参加することで、選ばれた役職が「支持されて役職になった」という自信につながります。
一方で、投票する側も「学校生活をよりよくするために自分が選んだ」という気持ちになり、生徒会に親近感を持つことができます。また、18歳以上から始まる選挙へのイメージも同時に持つことができます。
ただし、投票する側には「どうせ何も変わらないんでしょ」という思いから、いい加減に投票する層が一定数いることも事実です。
続いて、推薦です。教師や生徒によって推薦された人物が役職となります。適任者を選びやすいというメリットがある一方で、全校生徒からすると「勝手に決まっていた」と思われかねない決め方です。
生徒会長は、強いリーダーシップを持っていること、教師とも議論ができることが求められます。選定基準に沿った人物を推薦できるので、最も適任なスキルを持ち合わせた会長が誕生する可能性が高まります。
いずれの決め方も一長一短ではあるものの、生徒会を社会の縮図として学生に体験させるためには、選挙での決め方が適しているでしょう。
学生自治の基本組織である
生徒会は学生自治の基本組織として重要な役割を果たしています。生徒会を通じて、生徒たちは自主性やリーダーシップを学びます。自分たちで考え、計画し、運営していくという、イベントを一気通貫で行える組織です。学校行事やイベントの企画運営を通して、問題解決能力やチームワークの大切さも学ぶことができると言えます。
生徒会役職以外の生徒にも、自分の意見を採用してもらえるチャンスとして生徒総会が存在します。ここで意見を吸い上げられて、実行に移されたとき、自分が学校を変えたという意識と、学校は自分の意見を聞いてくれる組織だという意識が芽生えます。
生徒会とは、生徒会執行部として学校をよりよくする活動を行う生徒会執行部の役職にもメリットがあり、一見関係のない全校生徒にとっても意味のある組織なのです。

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-6.jpg)
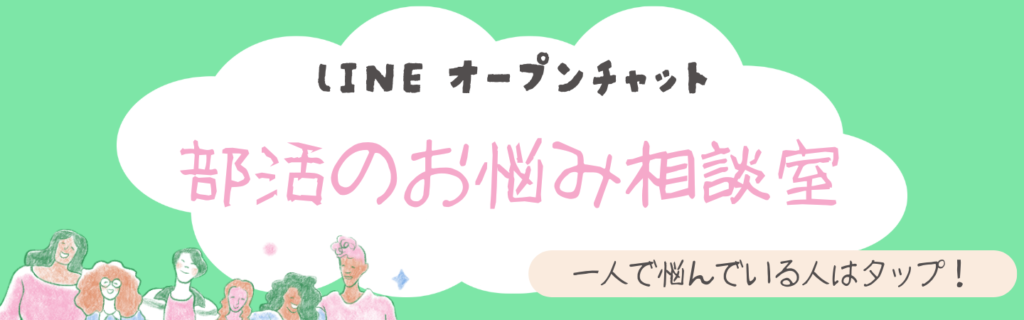

のコピーのコピーのコピー-23-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-7-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-4-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-25-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-22-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-3-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-15-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-1-300x173.jpg)
コメント