中学や高校での内申点に対してバカバカしい制度であると考えている人は一定数います。いくら実力があっても先生のさじ加減で点数がつけられてしまうのを不満に感じているのが多くの理由です。
「進学先に見合った学力をつけることが大切なはずなのに、実力以外の日頃の授業態度や提出物などで評価されてしまうのは納得できない」という意見もよく耳にします。
この記事では、内申制度に否定的な意見が出ている理由や、進学における内申点への対処法について詳しく解説していきます。
内申点とは?
「内申点」とは、受験の際に進学先に提出される内申書に記載される各教科の成績のことです。「評定」と呼ばれることもあります。
中学生が受ける多くの受験方式では、入試の点数だけではなく内申も合否の判断材料の一つとなります。大学受験でも指定校推薦や公募推薦の場合には、内申が加味されるのが一般的です。
受験への影響度が大きいため、志望校への合格の可能性を高めるためには評価の高い内申を取っておくことが重要となります。
内申点がバカバカしいと言われる理由
志望校の選択肢を広げるためには高い内申点を取らなければならないのが、今の高校受験や大学の推薦入試制度の実状です。しかし、この内申点を評価する仕組みの特性から、内申点という制度自体がバカバカしいことだと捉える人もいます。ここからは、その理由について詳しく解説していきます。
理由1 先生の好き嫌いで評価される
内申点は生徒に対する先生の好き嫌いで評価されてしまうというのが一つ目の理由です。
例えば、授業中に積極的に質問したり、授業の準備の手伝いをしたりといった行動が多いと先生からの心証は良くなりやすい傾向にあります。このような、先生に対して媚びを売れば評価が高くなるという仕組みに疑問を感じる人は少なくないでしょう。
勉強に対して熱心に取り組んでいる姿勢が評価されるのであれば納得できますが、先生に対する見せ方を子どもが意識してしまうというのは、教育的な観点からも懸念がありますよね。きちんと学力や姿勢など目に見える形での評価であれば、バカバカしいと捉えることもなくなるかもしれません。
理由2 ひいきされている人がいる
内申の評価について、生徒間でひいきされている生徒がいるように感じる人も多くいます。
例えば同じ70点という点数を取っている生徒でも、内申が3の人もいれば4がつく人もいます。テストの点数という勉強に対する実力は同じでも、日頃の学校生活や部活動、クラスでの様子などから評価に差が出ることもあるわけです。
生徒に対する先生の主観による判断が大きくなるため、えこひいきが起こっていると捉えられてしまうのです。学力以外のところでの判断は数値化できるものでもないため、ひいきが起こっている可能性は考えられるでしょう。
理由3 内申点だけ高い人がいる
生徒の成績を並べてみると、学力と内申点が一致していないというケースもあります。すなわち、内申点は4なのに、いざ実力を確認してみると基礎基本から理解ができていないということもあり得るのです。
逆に、内申点は低いのに、学力としては高く受験レベルにも対応できるという人もいます。このような逆転現象が起こっている事実があると、「内申点なんてくだらない」と思うのも納得です。
内申制度が廃止される可能性はある?
近年では、文部科学省に対して内申制度の廃止を求める提言が出されるなどの動きが見られています。
学力だけでなく、部活動や生徒会などの活動に取り組んでいる方が有利になったり、アピールが上手な生徒だけが得をしてしまっているという指摘がされています。
教師の顔色をうかがったり、どう評価されるのかを常に意識しながら学生生活を送ることは、子どもへの教育として不適切ではないかという意見が目立ってきています。
現時点で内申制度の廃止や変更の有無についての決定事項はありませんが、今後時代に合わせて変化していく可能性は十分に考えられるでしょう。
内申点が必要とされている理由
廃止を求める声がある一方で、内申点の制度が必要だという意見もあります。
内申点には、日々の学生生活での努力やコツコツと取り組んできた過程が反映されます。定期テストなどの一発本番の場ではどうしても緊張してしまい、いつも通りの実力が発揮できないという人もいます。日々の努力を評価してくれる内申制度は、そのような人たちにとっての安心材料の一つとなっていることも事実です。
また、進学先の視点に立っても「ただ学力が高ければ良い」というわけではありません。校風に合い、学校生活を充実させられる生徒に来てほしいという思いがあります。普段の生活を反映している内申は、進学先にとっては人物像を評価する上で大切な指標となっています。
見直すべきポイントがあるのは事実だとしても、内申制度をなくせば済むというわけでもありません。
内申点がゴミだったときの対処法
内申制度について賛否はあり、今後変化する可能性は考えられます。とはいえ、今はまだ進学を有利に進めるためには内申が必要です。高い点数が取れなかった時の対処法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
方法1 定期試験や小テストで得点を取る
内申点を今よりも上げなければならない場合、定期試験や小テストの点数を上げるのが最も確実な方法です。
学校のテストは試験範囲が決まっており、出題傾向もこれまでの試験問題からある程度予測を立てることができます。そのため、模擬試験などの実力テストと比べ、対策次第では得点を上げることができるでしょう。
目安として、内申点3を目指すなら60点、4を目指すなら80点、5を目指すなら90点以上を目指して対策に取り組みましょう。具体的な対策方法がわからなかったり、より確実に成果を出したい場合には、塾や家庭教師など、プロを頼ることもおすすめです。
方法2 提出物を期日内に出す
内申点の評価は定期試験の得点だけでなく、学習への意欲なども含め、総合的に判断されます。テストの点数がいくら高くても、提出物がおろそかでは内申点は低くなってしまうでしょう。出された課題は決められた提出日までに必ず提出するようにしてください。
また、内容の質を高めておくことも重要です。ただ解答を丸写ししたり、やっつけでとりあえず解いてしまっては、そもそも課題に取り組む意味がなくなってしまいます。学力を高めるためにもしっかりと取り組みましょう。内容についてもチェックされていますので、高い評価にも繋がります。
方法3 内申点が必要ない受験方式を検討する
内申点の影響を受けない受験方式を利用するのも一つの手段です。
高校入試であれば私立の中学校の一般入試は基本的に学力検査のみで合否が決められます。受験で通用する学力を習得し、実力勝負をすれば、内申点の影響を受けることはありません。
大学受験も一般入試であれば内申点が考慮されることはありません。実力さえあれば志望校へ合格できます。合格できるだけの学力を身につけましょう。
推薦入試では重視される
特に推薦入試を利用して進学する場合には、内申点は合否に大きな影響を及ぼします。進学先で定めている内申基準をクリアしていなければ、受験すること自体ができない学校も多いです。
入試本番で高得点を取る自信が持てない人や、勉強自体に強い苦手意識がある人は、推薦入試を利用できると合格の可能性を高められます。
現時点で現行の内申制度が設けられている以上、正しく仕組みを理解して、高い評価を得るためのコツを押さえながら、日々の学校生活を過ごしましょう。

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-3-1.jpg)
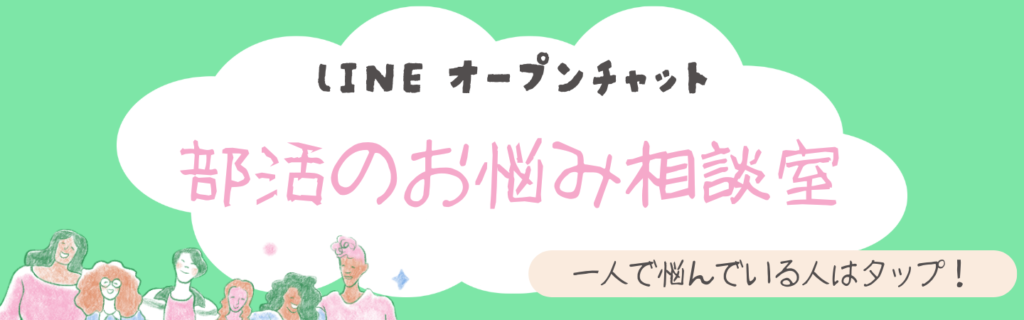

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-26-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-22-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-300x173.png)
のコピーのコピーのコピー-16-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピー-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-30-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-20-300x173.jpg)
コメント