「偏差値の低い高校」と聞くと、「将来が不安…」「勉強についていけないのでは?」など心配になる人も多いでしょう。しかし、本当に偏差値が低い高校に進学すると人生にマイナスなのでしょうか?
結論から言えば、偏差値だけで高校の価値を判断するのは早計です。偏差値が低い高校にも、それぞれ特色があり、生徒の将来をしっかり考えた教育を行っている学校がたくさんあります。
本記事では、偏差値が低い高校に対する一般的な不安を払拭し、日本一偏差値が低い高校の実態や、全国の偏差値20以下とも言われる高校をエリア別に紹介します。偏差値だけにとらわれず、自分に合った高校選びのヒントをお伝えします。
偏差値が低い高校への不安は本当に必要?
偏差値が低い高校と聞くと、「授業についていけない生徒ばかりでは?」「大学進学は無理なのでは?」といったイメージを持つかもしれません。しかし、偏差値が低い=学校や生徒の質が悪い、というわけではありません。そもそも高校の偏差値は入試の難易度を示すものであり、入試の点数や競争率によって決まる相対的な数字にすぎません。
例えば地方の高校では、受験する生徒数自体が少なく偏差値が低く出がちです。また専門学科(農業科、商業科、工業科など)を設置する高校や、全日制以外の定時制・通信制高校も、学科の特性上偏差値が低めになることがあります。偏差値が低い理由は地域事情や学校の募集人数、学科の特色など様々で、一概に「レベルが低い学校」と決めつけられないのです。
むしろ偏差値が低めの高校ほど、基礎学力の定着や生活指導に力を入れていたり、生徒一人ひとりに寄り添った教育を行っているケースも多々あります。大切なのは数字ではなく、「その高校で自分がどんな高校生活を送り、何を得られるか」です。不安に思うよりもまず、学校の実態や魅力に目を向けてみましょう。
日本一偏差値の低い高校はどこ?その実態に迫る
では、「日本一偏差値の低い高校」と言われる学校はどこなのでしょうか?
インターネット上で話題にのぼることが多いのが、静岡県の私立・誠恵高等学校(旧校名:沼津北高校)です。かつて俗に「日本一偏差値が低い高校」として有名になり、一時期は偏差値27とまで言われました。ネット上には「ぬまっき伝説」と呼ばれる同校の逸話が数多く出回り、「テストで名前を書くだけの問題が出た」「昼休みに生徒が帰ってしまうのでおやつ休憩がある」等、極端なエピソードが語られるほどです。
誠恵高校(旧・沼津北高校)の教育環境と進路
誠恵高校は確かに入学偏差値こそ低めですが、決して学習意欲が低い学校というわけではありません。むしろ、生徒の特性に合わせた多彩なコースを用意し、一人ひとりの将来に向き合った教育を行っています。例えば、同校には普通科(進学コース)のほかに、情報処理コースや芸術コースがあり、大学受験を目指す生徒には個別指導やオンライン教材「スタディサプリ」を活用した学習支援を行っています。体育実技を中心に基礎学力定着を図るコースもあり、基礎からしっかり勉強できる環境です。
近年まで誠恵高校の卒業生は就職希望者が大多数でしたが、大学進学を目指す生徒へのサポートを手厚くした結果、進学率も徐々に伸びてきています。実際、「理系科目の授業が少なく大学受験に不利」という声も過去にはありましたが、現在では必要に応じて補習を行うなど改善が図られています。「偏差値が日本一低い」と揶揄された誠恵高校ですが、生徒の将来を諦めず面倒を見る姿勢から、生徒思いで面倒見の良い学校と言えるでしょう。
誠恵高校のように偏差値が低い高校では入試問題も基本的な問題が中心となります。噂では「りんごを3つ持っているかずお君が…」といった極めて易しい問題が出たとも言われますが、実際には中学校の基礎内容をしっかり押さえていれば解けるレベルです。入試難易度が易しい分、高校入学後は基礎から丁寧に指導してもらえるので、「勉強についていけないのでは」という不安は必要以上に抱かなくても大丈夫です。
全国の偏差値20以下(?)の高校をエリア別に紹介
「偏差値20以下の高校なんてあるの?」と驚くかもしれません。実際には、全日制高校の偏差値で20台前半というケースはほとんどなく、2024年現在では偏差値30台中頃が最も低い水準です。ただ、「偏差値20以下」というキーワードで検索する人もいるように、それだけ非常に偏差値が低い高校に関心を持つ方が多いのでしょう。ここでは、全国各地の偏差値が特に低い高校を地域別にいくつかピックアップして紹介します。それぞれの学校の所在地や特色も合わせて見てみましょう。
北海道・東北地方
- 耶麻農業高等学校(偏差値35) – 福島県にある農業高校です。酪農や農業技術を学べる専門高校で、生徒募集数が少ないため偏差値は低くなっています。地域の農業を支える人材育成が目的で、生徒の多くは卒業後地元で就農したり、公務員(農業土木系)になるなど専門分野で活躍しています。なお、同校は現在は生徒減少により統合され、福島県立会津農林高等学校耶麻校舎としてその役割を継続しています。地域に密着した教育で、生徒に対する手厚い指導が行われている学校です。
- 北海道の過疎地域の高校 – 北海道にも偏差値が低めの高校が存在します。例えば北海道苫前商業高等学校(偏差値36)や礼文高等学校(偏差値37)など、道北・離島の高校は受験者数が少なく偏差値が低く算出されがちです。これらの高校では、商業科や地域産業科といった実務的な学科を設置し、卒業後は地元企業への就職や家業を継ぐ生徒が多い傾向です。少人数ゆえに教師と生徒の距離が近く、一人ひとりに目が行き届いた指導が受けられるのが特徴です。
関東地方
- 茨城県立真壁高等学校(偏差値35) – 茨城県桜川市にある高校で、普通科の他に福祉科など複数の学科があります。学科ごとに偏差値が異なり、最も低い学科が偏差値35となっています。地元では古くからある高校で、ロンドン五輪射撃日本代表の卒業生を輩出するなど部活動にも力を入れてきました。一方で口コミでは「やんちゃな生徒が多い」という声もあり、勉強一筋というよりのびのびと高校生活を送りたい生徒が集まる校風と言えるでしょう。授業の難易度は基礎中心で、中学内容の復習からスタートできるため学力に不安がある生徒も安心です。
- (関東近郊のその他の例) – 首都圏では全日制で極端に偏差値の低い高校は少ないですが、例えば**埼玉県立大宮工業高校 定時制(偏差値目安30台)**など、定時制課程では中学内容の学び直しから始められる学校もあります。都市部の定時制や通信制高校は偏差値という概念こそあまりありませんが、働きながら通う生徒や再チャレンジの場として多様な学生を受け入れており、自分のペースで学べる環境が整っています。
中部地方
- 愛知県立田口高等学校(偏差値35) – 愛知県北設楽郡設楽町にある公立高校です。普通科と林業科を有する特徴的な学校で、林業科の偏差値が35と全国でも最低水準です(普通科は偏差値40)。山間部の林業を担う人材育成を目指す専門学科のため入試競争率が低く、この偏差値になっています。生徒数は少ないですが、その分地域の林業体験実習や資格取得講座など実践的な授業が充実しています。2021年には男女とも同じデザインを選べるジェンダーレス制服を導入するなど、先進的で生徒思いの学校でもあります。
- 静岡県・誠恵高等学校(偏差値37) – 前述の誠恵高校(旧沼津北高校)も中部地方(静岡県)の学校です。偏差値こそ37と低めですが、普通科以外に情報・芸術系コースを設置し、多彩な進路に対応しています。就職希望者には資格取得やインターンシップ支援、進学希望者には映像授業での補習など、それぞれの進路に合わせたサポートが手厚いことで知られます。高校卒業後の進路は就職・専門学校が中心ですが、近年は指定校推薦などで四年制大学へ進学する生徒も少しずつ増えており、「偏差値=将来の可能性」ではないことを示しています。
近畿地方
- 東大阪大学柏原高等学校(偏差値35) – 大阪府柏原市にある私立高校です。複数のコースがありますが、普通科スポーツコースの偏差値が35と私立では全国最低クラスです。学力面で入学はしやすい学校ですが、実はここは硬式野球の強豪校として知られています。2011年には夏の甲子園大阪大会で初優勝し、甲子園出場も果たした実績があります。野球部以外にもサッカーやバドミントンで全国大会レベルの活躍をしており、「勉強よりスポーツに打ち込みたい!」という生徒にとって憧れの存在です。偏差値だけ見ると低いですが、その裏ではスポーツで輝かしい成果を出している文武両道ならぬ“武”に秀でた学校と言えます。
- 奈良県立西和養護学校高等部(偏差値—) – 偏差値とは少し異なる例ですが、近畿圏には学力試験を課さない特別支援学校の高等部や、受け入れ枠の広い私立校もあります。偏差値の数字では測れないこれらの学校では、生徒それぞれのペースに合わせた教育が行われています。例えば奈良県の西和養護学校高等部では、一人ひとりの発達段階に応じたきめ細かな指導が行われており、就労支援や生活スキルの指導など偏差値では表せない価値ある教育を提供しています。
中国・四国地方
- 島根県立隠岐島前高等学校(偏差値38) – 島根県隠岐諸島にある離島の高校です。地元の中学生はほぼ全員入学できる実質地元枠入試のため偏差値は低めですが、近年は独自の魅力が注目されています。廃校寸前だった同校は島留学制度などを導入し、今では島外からも生徒が集まる人気校に変貌しました。プロジェクト型学習や地域交流など島ならではの学びを提供し、生徒は東京大学や有名大学にも進学するなど成果を上げています。「偏差値=可能性の限界」ではない好例であり、偏差値にとらわれない学校選びの重要性を示しています。
- 高知県立嶺北高等学校(偏差値34~39) – 高知県の山間部にある公立高校です。全校生徒数が非常に少なく、一学年数十人規模の小さな学校ですが、地域と連携した課題解決型学習に力を入れています。偏差値帯はコースによって幅がありますが、最も低いコースが30台前半とされています。少人数教育の強みで先生の目が行き届き、生徒は林業体験や地元企業と協力した商品開発など実践的な活動を通じて社会性を育んでいます。大学進学よりも地元就職や専門学校進学が多いですが、それぞれの希望に合わせた進路指導が丁寧に行われる学校です。
九州・沖縄地方
- 宮崎県立高千穂高等学校(定時制)(偏差値目安30程度) – 宮崎県の山間部に位置する高校で、全日制の他に定時制課程を持っています。特に定時制は地域の若者や社会人の学び直しの場として開かれており、中学までの内容を基礎から教えてくれるため学力に不安があっても安心して通えると評判です。偏差値という概念はありませんが、受け入れの間口が広く、生徒それぞれの事情に合わせてゆったり学べる環境です。昼間は働きながら夜に通学する生徒もおり、卒業後は地元での就職はもちろん、大学や短大への進学を果たす人もいます。
- 沖縄県立沖縄水産高等学校(偏差値37) – 沖縄県の水産高校で、海洋技術科や食品科学科など海に関する専門学科を設置しています。偏差値は37程度ですが、実習重視のカリキュラムで船舶の操縦や潜水実習などユニークな授業が受けられるのが魅力です。卒業後は漁業・海運業界への就職、海上保安学校への進学、自衛隊や海上保安官として働く道など幅広い進路が開けています。また、同校はかつて野球の名門校として夏の甲子園準優勝の経歴もあり、スポーツ面でも伝統があります。このように学力偏差値だけでは測れない強みを持つ高校が九州・沖縄にも存在しています。
まとめ:偏差値にとらわれず自分に合った高校選びを
全国の偏差値が低い高校の例を見てきましたが、偏差値が低い高校にも多様な特色や強みがあることがお分かりいただけたでしょうか。確かに偏差値は高校選びの一つの目安にはなります。しかし、それは絶対的な評価ではありません。高校で何を学び、どんな経験を積むかは偏差値とは別次元の話です。
偏差値が低い高校だからといって将来が閉ざされるわけでは決してありません。例えば、離島の高校から難関大学へ進学したり、スポーツや専門技術の分野で全国レベルの活躍をする卒業生も数多くいます。大切なのは、自分の興味・関心や将来の目標に合った高校を選ぶことです。学力に自信がないなら基礎から丁寧に教えてくれる高校を選べばいいですし、勉強以外に打ち込みたいもの(部活や専門スキルなど)があるならそれを伸ばせる学校がきっと見つかります。
偏差値だけにとらわれず、学校説明会やオープンキャンパスなどに足を運んで実際の雰囲気を確かめることも重要です。先生方の熱意や先輩たちの表情、生徒の様子を見ると、その高校の本当の良さが見えてくるでしょう。高校受験は人生のゴールではなくスタートです。偏差値の高低に一喜一憂するより、自分にとってベストな高校で充実した3年間を過ごすことこそが、その後の進路や人生に大きなプラスとなるはずです。
偏差値が低い高校への進学を検討している人も、不安になりすぎず前向きに捉えてください。どの高校を選んでも、自分次第で道は切り拓けます。今回紹介したように、日本一偏差値が低い高校であっても生徒の可能性を伸ばそうと工夫を凝らしている学校ばかりです。
ぜひ視野を広げて、多様な高校の中からあなたにピッタリの高校を見つけてください。偏差値に惑わされず、充実した高校生活への一歩を踏み出しましょう!

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-21.jpg)
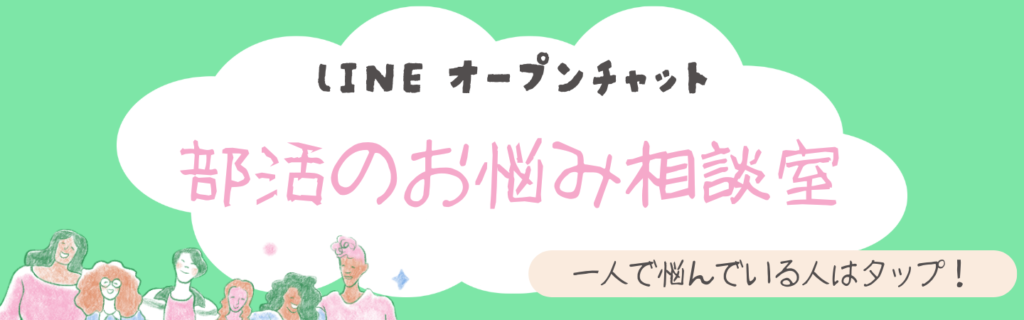

のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-1-1-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-6-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-19-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-23-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-300x173.png)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-9-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピーのコピーのコピー-29-300x173.jpg)
のコピーのコピーのコピー-2-300x173.jpg)
コメント